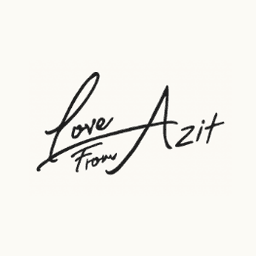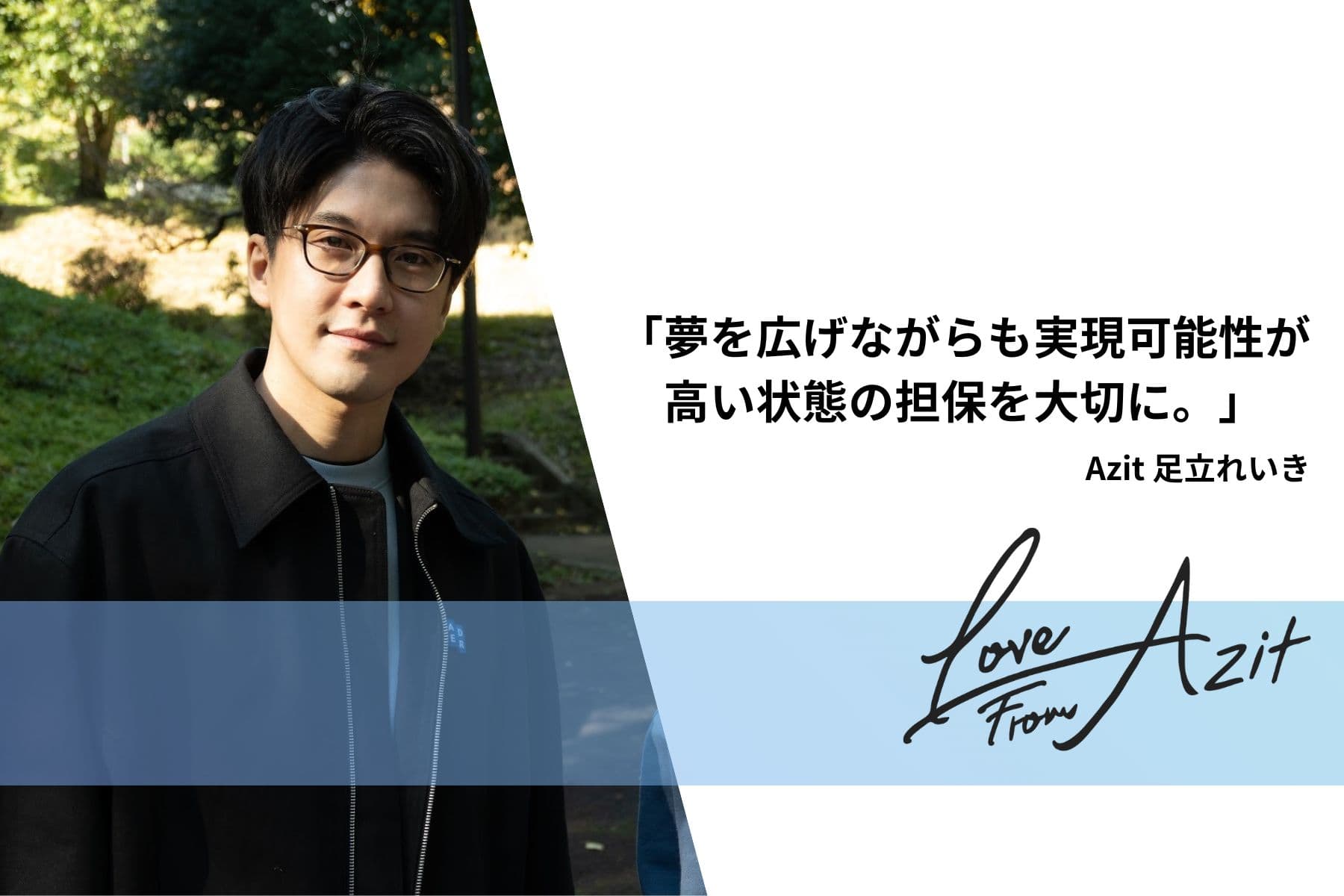
今回お届けするのは、サクセス部の部長 兼 パートナーアライアンス室 室長を務める足立のインタビューです。1号社員として創業初期のAzitに参画してからピボットを経て今に至るまでを深掘りしました。
PROFILE
足立れいき @reikixs
大学在学中のインターンで現CEOの吉兼と出会い、法人化前のAzitに参加。2015年 株式会社リクルートホールディングス(現:株式会社リクルート)に新卒入社。その後、再びAzitへ合流。
とにかく前を向き続けるチーム
— Azit1号社員でしたよね
当時はライドシェア事業を開始した時期で、それこそ1日1回使われるか使われないかくらいだったと記憶しています。役割としては、それまでの経験もありマーケティング職として入社しました。
— 入社当時のAzitはどのような状況でしたか?
前進していくぞという空気感が強かったです。平均年齢25歳とかだったので、言ってみれば小難しく考え込めるほどの経験もなく、Aと決めたら「Aだ!」Bと決めたら(以下同文)の様な勢いで会社が前進していたと思います。
— マーケティング職とのことですが、当時の仕事内容について教えてください
最初は広告運用や、初回利用体験の改善みたいなところから始めました。そのうち、ドライバー側の集客とオンボーディングが課題となってきたので、オペレーションのフロー化を始め、CRM導入や運用体制の構築を行いました。ドライバーの皆様に対応いただく必要書類の提出の電子化などもやっていましたね。今思うとDXっぽいですね。
事業が伸びるにつれて、チームが大きくなってきたので、マネジメントに加え、ブランド方針策定から施策の実行までをやっていました。
ー 整理解雇もありましたが、Azitに残ろうという決断の理由はなんですか?
たしかに。整理解雇を経たからといって残留する義務が生じるわけではないので、辞めてもよかったですし、それを阻止するような雰囲気もありませんでした。
言われてみて考えると、私としては大学時代の知り合いのチームに再合流したと捉えていたので、「Azitに“転職”した」という感覚はあまりありませんでした。なので、辞めるとか他に移るっていう選択肢が浮かばなかっただけな気がします。
また、たまに質問されるのですがキャリア面でのリスクについては、スタートアップが訝しがられていた時代からずっと、リスクなしと判断しているのでそこの恐れは当時もなかったです。
ー その後ピボットをして苦労してきましたよね
Azitはその時点でtoC事業の経験のみを持っていたチームでした。なので、今のDeliveryXをはじめとするtoB事業に求められる考え方や所作・振る舞いを分かっていませんでした。その学習にとても苦労したなと思っています。事業を成長させるためには自分たちが変わらないといけなかったこともあり、結果変われたという実感はあります。でも、やり直せるならもっと短縮できるんじゃないかと思う点は多いですね。
ー その中で、役割はどう変わったのでしょうか
ライドシェア事業の頃はマーケティング職で入り、ブランディング全般も担うようになりました。オペレーションマネージャーもやっていましたが、いわゆるマーケティング部のマネージャーという役割だったと思います。
一方で、ピボット後はいわゆる広告宣伝みたいな機能は設けずにセールスによる企業獲得が主軸になりましたし、ブランディングについても優先度は落ちたので、オペレーションマネージャーの役割をメインに動きはじめました。
主なミッションとしては、クライアントの配送に関わる業務フローをDXしてやれることを増やす、売上を増やすということでしたので、過去の経験含め上手く自分のケーパビリティを活用できた気がします。
事業が成長するにつれて、DXができたあとに、「荷物誰が運んでくれるんだっけ」という局面で困るクライアントが増えてきたので、その課題を解決するためにフードデリバリー各社とシステム連携を行い、サービスを拡充していきました。その中で、各社とのアライアンスのミッションを持つことになり、提携の条件交渉と契約締結までなどアライアンス業務が増えてきました。この時点で、狭義のマーケティング職とは少し違う役職になったと思います。
ただ、今は、クライアント企業のサクセスの責任も併せて持っており、これは結局のところ「配送網拡大により売上を上げたい荷主」と、「荷物をたくさん運びたい配送ネットワーク」を結びつけることなので、本当の意味でのマーケティングであると感じています。
ステークホルダーの機微を見逃さない
ー Azitのサクセス / パートナーアライアンスとして重要なことはなんですか?
顧客の努力を無駄にしないことです。
私達は配送手配のアグリゲーターサービスを展開しています。この事業では、「複数の事業者の取引規格を統一し、売り手と買い手の流動性を上げる」ということが重要なのですが、ここで各事業者を統一規格に“押し込めて”しまうと、その統一規格自体がボトルネックになってしまいます。
例えば、配送ネットワークのうち一社が「荷渡し時のサイン機能」を一生懸命開発して利用可能にしたとしても、私達アグリゲーターがその機能を開放しないと、荷主もそのオプションを選べません。
逆も然りです。荷主が「配送効率化のため、荷物の到着期限を3日まで延長しました」といっても、アグリゲーターが当日配送しか規格をもっていない場合、荷主の企業努力が無駄になってしまいます。
たとえそれが私達からニッチに見えたとしても、たった1社のみの 機能 / 対応 だったとしても、それが必要かどうか判断するのは本来アグリゲーターではなく 配送ネットワーク / 荷主 のはずです。
それに、アグリゲーターがそのような振る舞いをしてしまうと、参加している各社の企業努力による 商品改善 / 要求緩和 を無意味なものにすることになります。結果として、業界全体の熱を冷ますことにつながると思っています。
日本ではまだまだデリバリーの利用が少なくポテンシャルもある分、業界全体でできることを増やし、市場を立ち上げていかなければいけません。
なので、荷主と配送ネットワークに互換性をもたせることは当然として、双方の制約を1mmでも取り払うことがDeliveryXの使命だと思っており、大切にしています。
ー その中で仕事を進める上で決めていることは
実現可能性の担保から逃げないことです。DXって、理論上技術的にはどんなことだって実現できるのですが、そういった一見夢膨らむ話をしているときに、クライアント出席者のうちの一人の表情が曇ってたりすることがあって、そういうのを見逃さないようにしています。
会議室全体は両社ともに夢が広がって大盛り上がりなのですが、きっとその人にだけ見えている、実現ハードルや懸念点があると思うんですね。その時に、きっとここを気にしているだろうなっていうのが感じられることがよくあります。
その場でぱっと解決策を伝えてもいいし、「こういう懸念がありますよね、そこは放置しません」と伝えるのでもいいんですが、そういうところから逃げずに全員が前向きな気持でプロジェクトを進められるよう、実現可能性が高い状態の担保を大切にしています。
採用情報
Azitではクライアントサクセス|カスタマーサクセスのポジションを募集しています。詳細は、以下の募集ページをご覧ください。
https://herp.careers/v1/azitinc/r14R9Ev01j2d
また、Azitではpodcastも配信しております!ぜひ聞いてください!