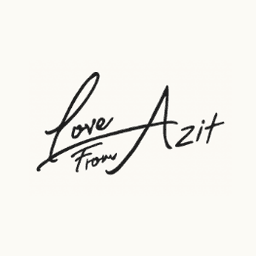.png&w=3840&q=75)
Azitを卒業し、別の場所で挑戦を続ける“ex Azit”の仲間たちに、Azit代表の吉兼が話を聞くインタビュー企画「ex Azit」。第二弾に登場していただくのは、株式会社HRBrain 取締役CFOの作井 英陽さんです。
投資銀行でキャリアを重ね、2018年にAzitへ。財務担当執行役員/コーポレート本部長として、会社の成長に伴走しながら資金調達とコーポレート体制をけん引した作井英陽さん。その後JDSCやHRBrainの取締役も務めた彼に、Azit時代に培った視座と、今なお印象に残る「Love」の意味を聞きました。
PROFILE
作井 英陽さん
東京大学経済学部卒。2013年よりUBS及びメリルリンチにおいて投資銀行業務に従事。2018年より株式会社Azitにて財務担当役員。2020年より株式会社JDSCの取締役CFOとして創業2期目から6年間のIPO前後の経営を担い、ソフトバンク、SCSK、ダイキン工業、中部電力といった大手企業との戦略的な資本業務提携や、複数のM&Aの実行等を通じて、企業価値向上に貢献。経済産業省 スタートアップ・ファイナンス研究会の理事を務める等、未上場からグロースの資本市場の活性化にも尽力。2025年より株式会社HRBrain取締役CFOに就任し、現在に至る。
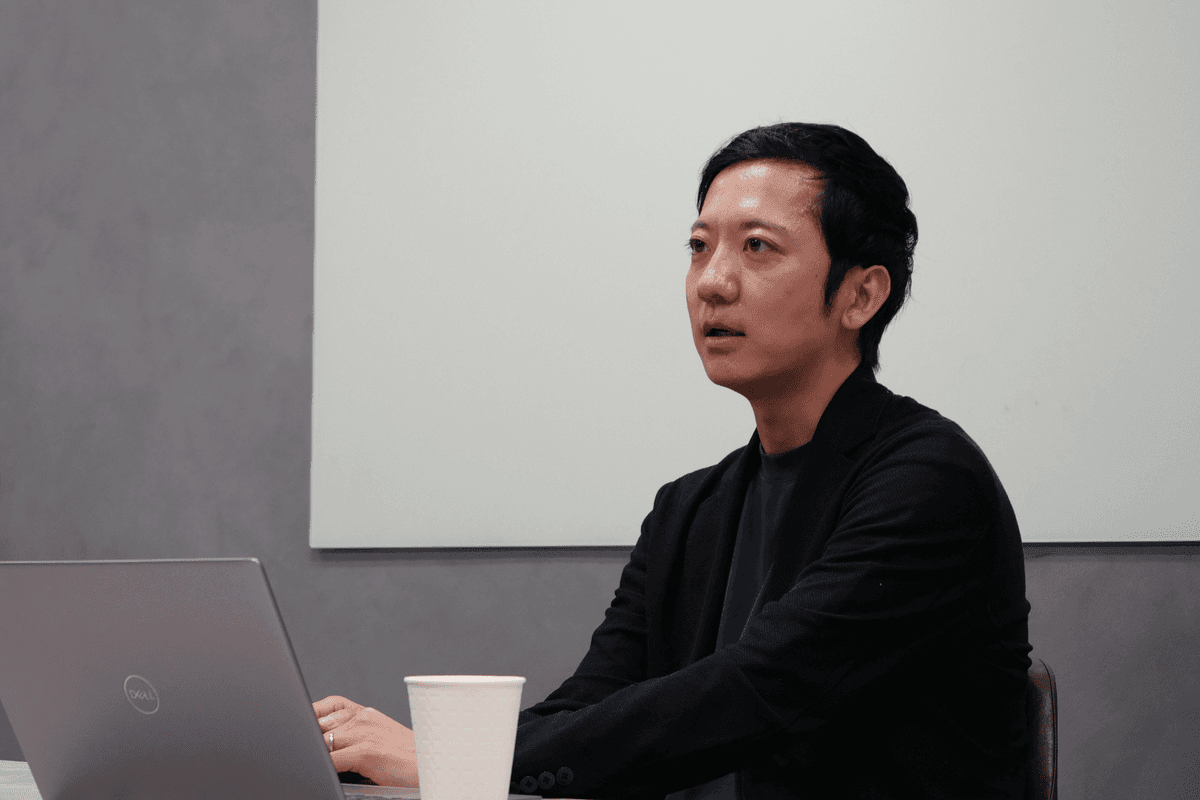
作井 英陽さん
参画の決め手は『人』。カルチャーのシンクロが背中を押した最終面接
ー 本日はよろしくお願いします。まずは、当時Azitでどのようなことをされていたか教えてください。
もともと投資銀行にいて、2018年にAzitに入社しました。初めての事業会社でしたね。Azitでは、コーポレートマネジメントと資金調達や財務戦略などを統括していました。
当時のAzitは配車プラットフォーム「CREW」のトラクションがものすごい勢いで伸びていた時期です。それこそ、JDSCが年間で追っていたような30〜40%のグロースが、月次で叩き出されているような驚異的な時期でしたね。そういったKPIを前提に、ファイナンスにトライしていました。
ー あの成長は、まさにtoCならではでしたよね。当時、まだまだ経営体制が整っていない中、CFOは最も大事なポジションだと定義して採用活動を行っていました。ちょうど、現共同代表の山口や他CXO候補者の方々が内定していたくらいの時期ですね。CREWは、特にファイナンスが難しい事業で、この領域は海外の事例を見ても、資金調達力が事業成否を左右していることは確かでした。資金調達専任の人が必要だと思っていたし、周りからもCFOにいい人が入ると良いね、という言葉を言われていました。半年以上探してたくさんの方にお会いしてきたのですが、その中で、作井さんに会ったときに、すごく誠実さを感じたのを覚えています。
ある意味、金融出身の人ならではの「色」というのはありますからね。
ー そうなんです。どちらが良い悪いではなくて、Azitは結構価値観やカルチャーを大事にしているのですが、金融業界の方々とは考え方や大事にするポイントが少し異なり、フィット感の高い方を見つけるのに苦労していました…。当時の僕たちとお話をしてくださる方って、それこそスタートアップへの関心が高い、感度の高い方ではあったと思うんです。それだけでなく、人格者でもある作井さんにお会いして、「この人にオファーしたい」と素直に思いましたね。
それは嬉しいね。自分自身のやりたかったこととしては、もちろんスタートアップというものに憧れていたこともあるし、当時世界にはUberやDiDi、Grabなどがある中で、Azitは日本発として立ち上げて、Eight Roadsなどからも資金を受けている段階。ただ、まだ20〜30人くらいの規模で、ここからシリーズBに突き進むようなフェーズは、自分のようなファイナンシャルな目線からみても面白いと感じました。そして何よりもやっぱり、人が魅力的だと思ったので、入社を決めました。
ー 最終面接のあと、メンバー5人くらいに面談をしてもらったのを覚えています。
そうそう。その時驚いたのは、示し合わせていてもできないようなシンクロ率を発揮していたこと。組織やカルチャー、人に対することを、同じような言葉選びや表現をしていたのが、当時の自分から見るとすごく良かったんですよね。
ー 当時から、示し合わせてはいないけど、皆が同じ方向を向いている組織ではありましたよね。
あと、入社してすぐの合宿も印象的でした。熱さも含めて、いわゆるスタートアップの合宿らしくて良かったですね。その後組織は何倍にも拡大していきましたが、大きくなってもリファラル率が高かったし、今もすごく参考にさせてもらっている最終面接のやり方なんかも、変な人が入らない仕組みがしっかりと存在していて、組織の成長に大事なことが備わっているな、と感じました。
ー 最終面接のやり方は、僕自身のこだわりでもあります。(詳しくはこちらの記事でご紹介しています)
僕自身、Azitのときは組織作りに比重を置きすぎたと思って、実はその後の選択では逆張りしてみたんですが、やっぱり上場後に人がたくさん辞めたりしたことも含めて、組織カルチャーへの投資は大事だなと改めて思わされましたね。
ー 組織作りって、なかなかROIで考えにくいですもんね。
少し語弊があるかもしれませんが、バランスの取れた組織を作るのってすごく大変で。ある意味、ぬるい組織を作るのは簡単なんですよね。事業成果を出すために軍隊的な組織を作るのも簡単。そうではなく、事業成果にコミットしつつ心理的安全性も保てるようなバランスの取れた盤石な組織、いつかは成功させてみたいですね。
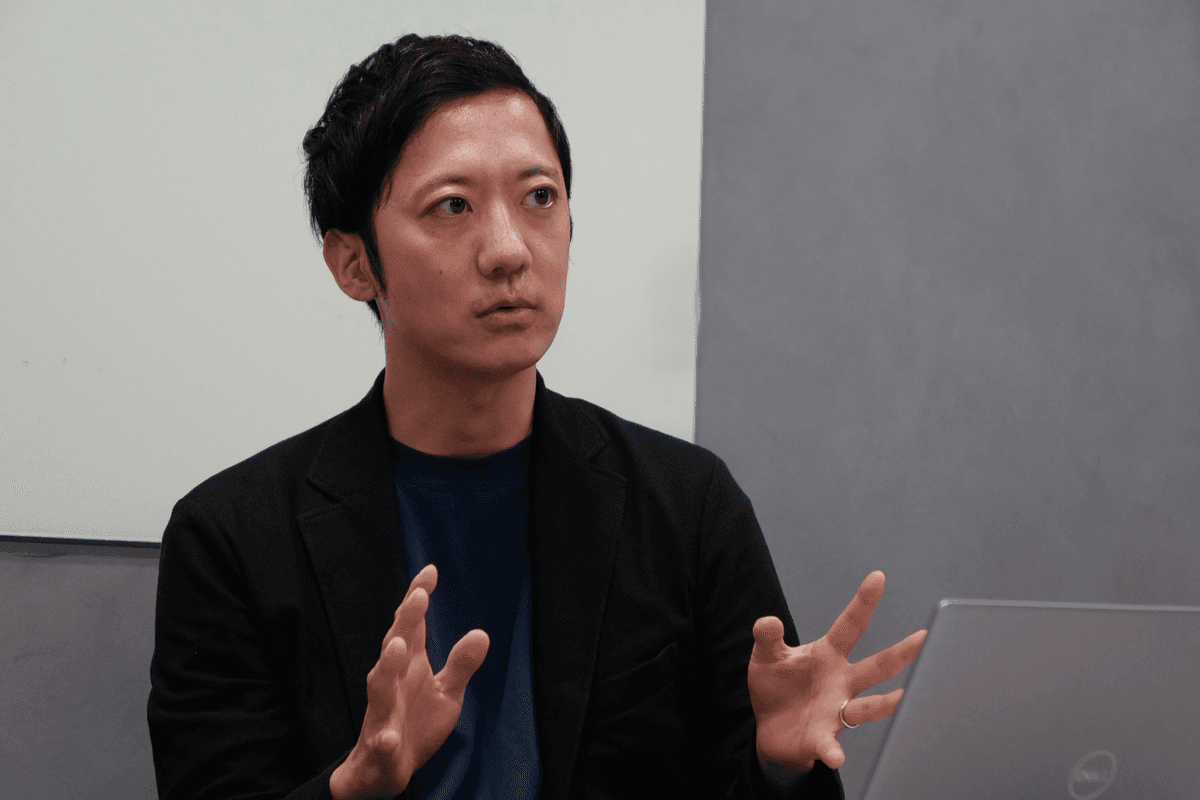
資金調達、VALUEの再定義。Azitで学んだこととは
ー Azitで印象的だった出来事はありますか?
資金調達に関してはきつかったですよね。結果というよりは、プロセスのキツさがありました。
でも、印象的だったのは、Azitのメンバーが当時もすごく前向きだったことです。どんな状況でも心が折れないというか、前を向いてやり切る気持ちがありましたよね。
正直、僕個人に関して言うと、当時ピボットに関しては覚悟が足りていなかった部分があったと思います。ライドシェアを前提に大きなファイナンスで動き続けてしまったし、今考えるともっと違ったプランも提示していくべきだったな、と思う所はありますね。それもあって、JDSCでは圧倒的なコンサバファイナンスだったのですが(笑)
ー たしかに、あんなにしんどいファイナンスはなかったですが、ある意味では、あんなに楽しいファイナンスもなかったとは思うんです。もちろんそれは「funny」ではないのですが。映画を見ているような迫力のファイナンスという意味では印象的でしたし、体験価値も高かったと思うんですよね。
それはそうだね。あと印象的だったのは、バリューの再定義のプロジェクトをやったときのこと。当時のバリューを定義するとき『Love』という単語について、深く話し合った記憶があって。
Loveって、日本人の多くは少し遠慮しちゃうというか、ちょっとまっすぐ捉えられない恥ずかしくも思ってしまう単語だと思うんですよね。でもAzitの皆は当時もそして今も、その単語を違和感なく使える。経営陣がその雰囲気を体現していて、それが僕は好きだった所です。自分はちょっと気恥ずかしさを感じてしまうので(笑)
ー まあ、普通ちょっと恥ずかしいというのも理解しています(笑)
でも、それを「ちょっと恥ずかしいよ」って言える心理的安全性もAzitにはあるよね。それがやっぱりめちゃくちゃ強い部分だと思うし、誰かが入社したとき、その人がDay1から安心して活躍できる組織のOSだと思うんです。
このオウンドメディアのタイトルもLove from Azitで「あぁ、あのVALUEが残っているんだ」と思うと安心しました。
ー 今のVALUEも『Love & Respect』なんですけど、たしかにその頃から変えたんでしたっけ。
当時『Respect For All』だったのを変えたんだよね。吉兼がこだわってたのが印象的で。社会に対する自分たちが大切にしていることとして真剣に語っていて、そこがAzitらしいなと当時から思っていました。
そういうハートウォーミングな部分と、一方で今のスタートアップ業界で見ても遜色ないレベルのメンバーたちが、かなりの強度で毎日を過ごしていて。もちろんマーケットやタイミングで結果は変わってしまいますが、ハードにやりつつマネジメント陣も平気でいじられたりするような温かい雰囲気って、実はすごく作るのが難しいんですよね。逃げずにやり切るスタンスも含めて。それがAzitで印象的でした。
泥臭さとプロダクト開発の両輪。そしてその先へ
ー 現在の成長された作井さんとして、Azitの経営に対してアップデートできる要素を考えるとしたらどういう所でしょうか。
今のAzitがやっているような物流・サプライチェーン領域に入っていくという選択はとても良いなと思っています。エンプラの方々、特にマネジメント層のそこへの危機意識ってすごく高いですし。モダンなUIでその領域のシステム開発ができる人たちってなかなかいなくて、だからこそJDSCのようなAI系のコンサル開発企業も重宝していただけるわけですが、Azitもその領域のチャンスは多分にありますよね。
もし何か提言するとしたら「もっと泥臭く覚悟を決めてやってもいいんじゃないか」ということでしょうか。例えば、システム開発領域なんかも。現状コンサルをやっている企業には、なかなかAzitのようなテックスタックがある企業はないですし、そこにはまだスペースがあるはずだと思います。
ー ありがとうございます。たしかにですね。ちょうど最近需給予測のプロダクト(Azit、生成AIを活用し低価格・短期間で導入できる需給予測プラットフォーム『ForecastX』を正式リリース)を出したのですが、それによって対象企業はかなり広がりました。物流だけでなく、製造業や流通業の方にもアプローチすることができるようになり、よりセールスの力を活かしやすくなりましたね。
また、需給予測をした後のS&OPの業務、例えば在庫管理や発注管理、生産量を決めるなどのプロセスにExcelを使っているような企業の方が、DXしたいというお話をいただいたりもします。どこまでをプラットフォームで解決して、どこまでをカスタマイズして解決していくかを決めていかなくてはいけないフェーズにありますよね。

吉兼 周優
ー これからAzitに興味を持ってくれる方へ、メッセージをお願いします。
Azitの魅力は大きく2つあると思っています。1つはマーケットですね。物流・サプライチェーンという領域、特に日本でいうと、全産業を並べてもマーケットサイズがかなり大きいし、労働人口の減少がクリティカルに響いてしまう分野でもあるのですが、それをモダンな技術を駆使して解決できる手法があるかというと、まだ多くはありません。例えば、ヘルスケアや通信領域などは各企業の中にもそういった部分に長けている人材も多いですが、物流領域はそうではないので、スタートアップとしてジョインして大きな解くべき課題に対して自分たちがどれだけ求められているかっていうマッチが高い領域なので、そういうマーケットに身をおいた方が成長する機会が多いだろうと思うんですよね。
2つ目は『人』です。スタートアップに飛び込むからには、一緒に働く人から大事なものを学んだほうが良いと思っています。Azitにいるメンバーは、本当の意味でスタートアップらしいというか、諦めない素質や胆力があって「この仮説がだめならこっちをやる」という、スタートアップらしい事業作り、スタートアップ作りの真髄は、皆から学べると思います。
どちらも大切ですが、特に後者はかけがえのないものだと思います。僕自身もAzitで強く学ばせてもらったところですし。
ー ありがとうございます。教科書的な意思決定の下支えとなる地盤のようなものですよね。
まさに。『ハードに働く』とかは、プロフェッショナルファームでも事業会社でも経験している人はしていると思うし、もしそういうハードワークができる人はもちろんぜひやったら良いと思うんですけど、それだけじゃない、真の意味で試されるときってあると思っていて。そういう局面を体験できるのって良いと思うんですよ。それは、決して心が追い詰められるような意味ではなくて。Azitって、その緊張感と楽しさと温かさ、それこそLoveのような気持ちを持って働いている人たちがいるから、きっと安心して学べるはずです。
聞き手:吉兼周優 編集:坂井華子
採用情報
Azitでは、各職種で採用を行っております。詳細は、以下のページをご覧ください。
https://herp.careers/v1/azitinc